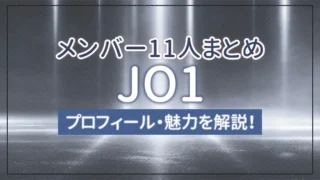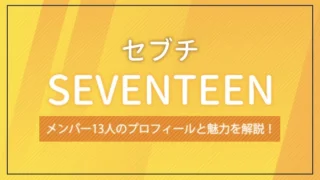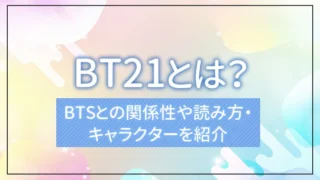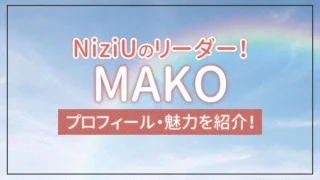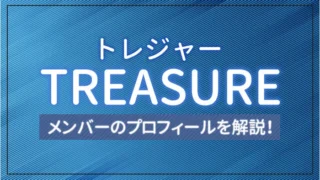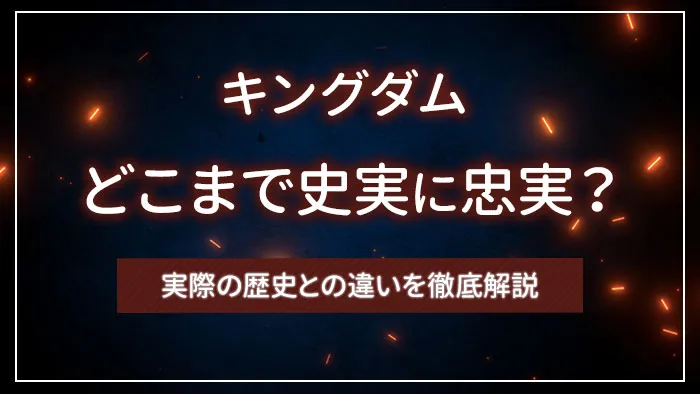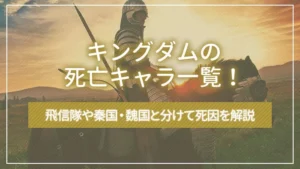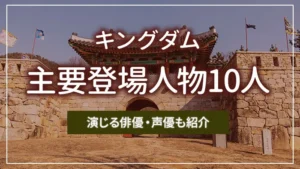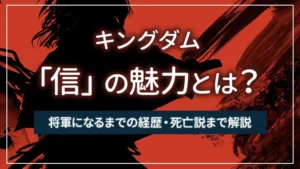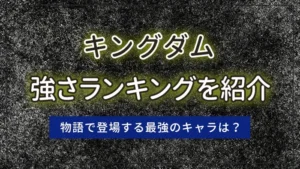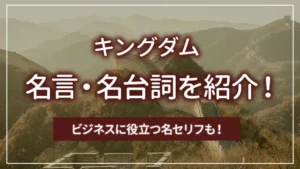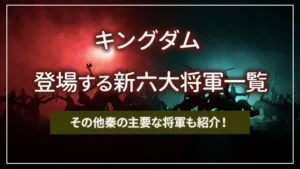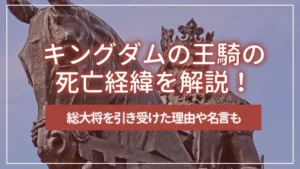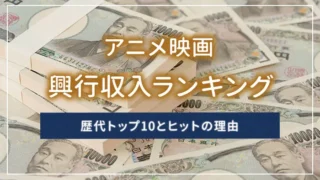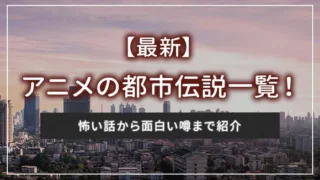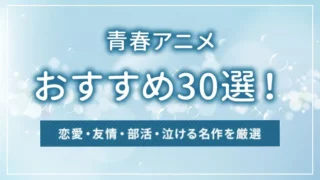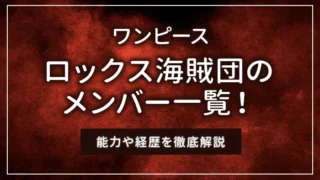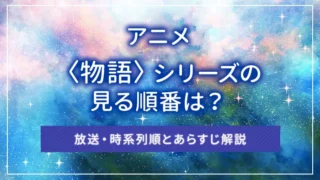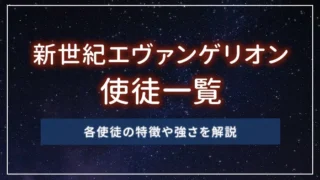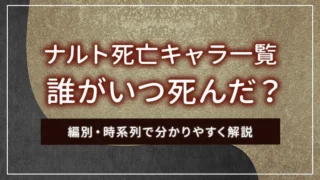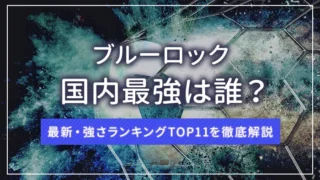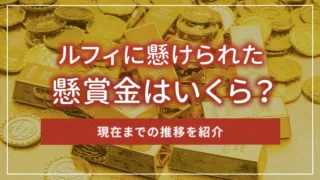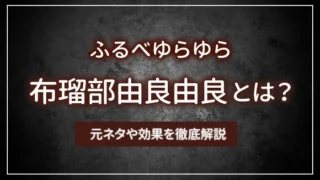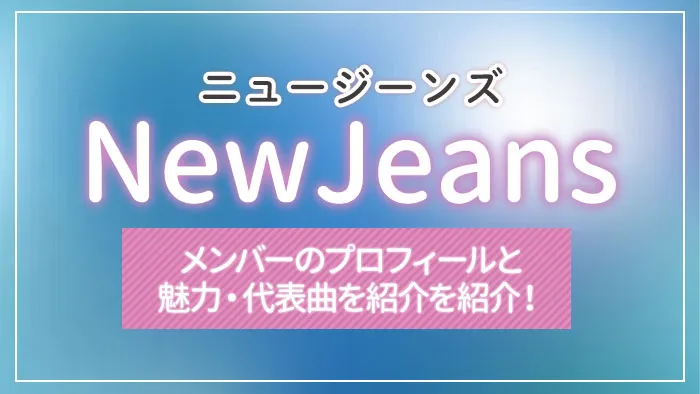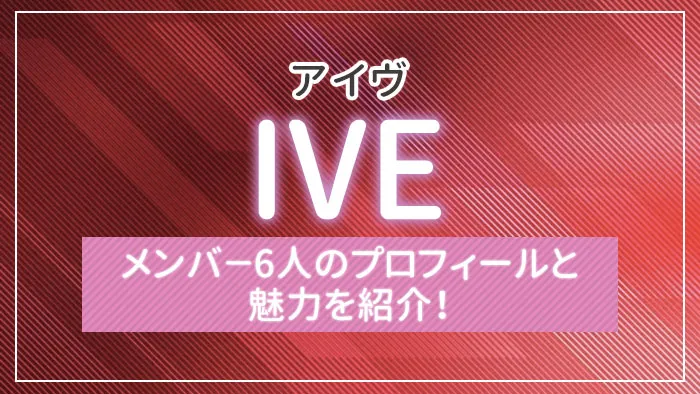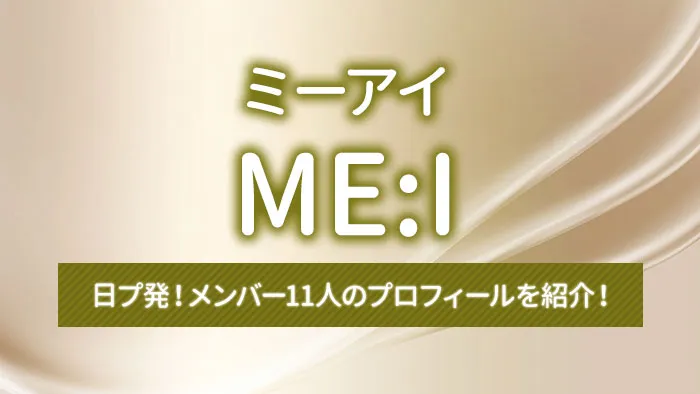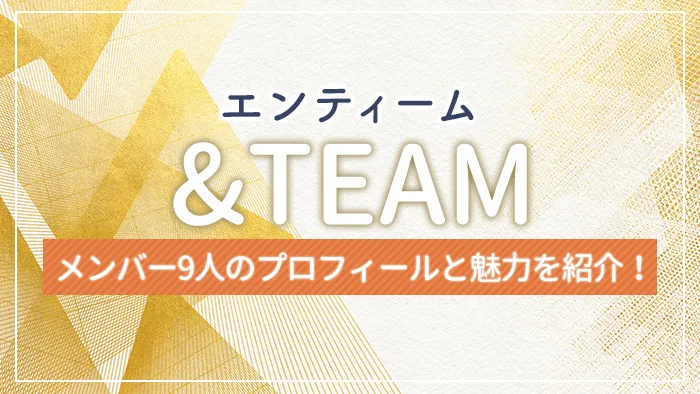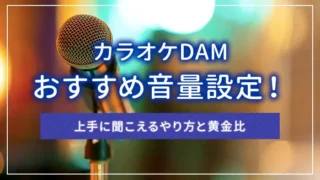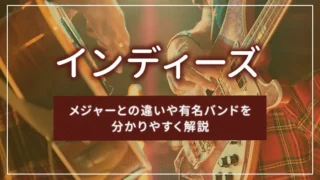漫画『キングダム』は、春秋戦国時代末期の史実を背景に描かれた壮大な物語です。秦王・嬴政と若き武将・信を中心に、中国統一へと進む道程を活写しています。
しかし作品は歴史を忠実に再現したものではなく、史実と異なる順序や人物像の再構成が多く見られます。作品の中には、実在の人物に基づくキャラクターもいれば、物語を盛り上げるために創作された人物も存在します。史実との違いを理解すると、物語の背景や演出の意図がより深く見えてくるでしょう。
当記事では、キングダムの各巻が史実とどのように対応しているのかを整理し、その上で作品ならではの脚色や魅力を解説します。
1. キングダムの各巻と史実の流れの比較
/
— キングダム公式アカウント (@kingdom_yj) July 17, 2025
キングダム76巻 本日発売!!
\
『キングダム』最新コミックス第76巻本日発売です!白熱する韓討伐戦、副将を任された信は挑み来る韓軍を打ち破れるか…!?
ご購入はこちらから!https://t.co/OYeLVrtLyG#キングダム pic.twitter.com/nVWYKH7WMM
漫画『キングダム』は史実を下敷きにしつつも、物語的な脚色が加えられているため、史実と完全には一致していません。ここでは、年表形式で史実と漫画の流れを紹介します。
【史実・春秋戦国時代の年表とキングダムの各巻】
| 年代(紀元前) | 史実の出来事 | キングダムの巻数・編 |
|---|---|---|
| 259年 | 嬴政(後の始皇帝)誕生 | (描写なし) |
| 247年 | 荘襄王が死去。13歳の嬴政が秦王に即位。呂不韋が相国となり後見人に | 1~5巻(王都奪還編)、5~7巻(蛇甘平原編)、8~10巻(刺客急襲編) |
| 245年頃 | 信(李信)が登場(史実では秦の将軍) | 主人公・信の少年時代開始 |
| 244年 | 蒙驁が韓を攻め十三城を取る。王齮死去 | 10~16巻(馬陽防衛編)、17~24巻(山陽平定編) |
| 241年 | 楚・趙・魏・韓・燕の五国合従軍が秦に侵攻。秦は函谷関で撃退 | 25~34巻(合従軍編) |
| 239年 | 成蟜が屯留で謀反、討たれる | 34~35巻(屯留編) |
| 238年 | 嬴政が成人し実権掌握。嫪毐の乱。呂不韋失脚 | 35~37巻(著雍攻略編)、37~40巻(毐国反乱編)、41~46巻(黒羊丘編) |
| 236年 | 王翦・桓齮・楊端和が趙を攻め、鄴を含む九城を攻略 | 46~60巻(鄴攻略編)、60~62巻(什虎攻略編)、62~64巻(武城・平陽編) |
| 235年 | 呂不韋が嫪毐の乱への関与を疑われ自殺 | 60巻 |
| 234年 | 桓騎が趙を攻め、扈輒を討つが李牧に敗れる | 65~73巻(趙北部攻略編) |
| 233年 | 韓非が秦に召される | 69~70巻 |
| 230年 | 秦が韓を滅ぼす | 73~76巻(韓攻略編、進行中) |
| 228年 | 秦が趙を滅ぼす | (今後の展開) |
| 225年 | 秦が魏を滅ぼす | (今後の展開) |
| 223年 | 秦が楚を滅ぼす | (今後の展開) |
| 222年 | 秦が燕を滅ぼす | (今後の展開) |
| 221年 | 秦が斉を滅ぼし中国統一。嬴政が「始皇帝」となる | 春秋戦国時代終結 |
漫画では史実と異なり、戦いの順序や描かれ方が変化しており、キャラクターの成長や物語展開を際立たせる演出がなされています。
1-1. 史実における七雄の滅びる順番
戦国時代末期、中国の七雄と呼ばれる国々は秦の台頭によって次々と滅ぼされました。史実で最初に滅んだのは韓で、紀元前230年に秦の将軍・騰によって王安が捕らえられ、国は消滅しました。
続いて紀元前228年には趙が滅亡します。最大の強敵であった李牧が、王の疑いにより処刑されたことで国力を失い、王翦率いる秦軍に邯鄲を攻略されました。魏は紀元前225年、王賁による黄河の水攻めによって首都・大梁が崩壊し、降伏を余儀なくされます。
その後、紀元前223年には楚が王翦の大軍に敗北しました。楚は広大な領土と兵力を誇ったものの、昌平君を王に立てた抵抗も実らず滅亡します。紀元前222年には燕が王賁の軍に攻められて滅び、最後に残った斉も紀元前221年、降伏することになります。
こうして秦はわずか10年足らずで中華統一を実現しました。
2. キングダムと史実の違い6選
ㅤ
— 映画『キングダム』公式アカウント (@kingdomthemovie) July 11, 2025
━━━━━━━━━━━
映画『#キングダム』
2026年・夏
続編公開決定
━━━━━━━━━━━
大将軍の意思を継いだ者たちが
再び立ち上がる——
《スーパーティザー映像解禁》 pic.twitter.com/aGgS7yMLfe
『キングダム』は史実を土台にしつつ、人物像や合戦の順序、組織設計などに物語上の再構成が加えられています。史料に基づく確かな事実と、読者の感情移入を高めるための脚色が混在しており、史実と照らし合わせる視点を持つと理解が深まります。
ここでは、代表的な違いを6つ紹介します。
2-1. 嬴政は猜疑心が強く苛烈な性格だった
漫画では、嬴政は理想に燃える若き王として描かれ、民や仲間に慕われる姿が印象的です。しかし史実の始皇帝は、徹底した中央集権体制を築く一方、強い猜疑心を持つ苛烈な支配者という印象がある人物です。資料には、反乱を恐れて側近や一族を処罰した記録や、厳しい法をもって民を統治した記載が残されています。
つまり、作品で描かれる人情味あふれる名君像と、史実における恐怖と法で支配した実務的な君主像には大きな隔たりがあると言えるでしょう。
2-2. 蛇甘平原の戦いはフィクションである
序盤で信が初陣を飾る蛇甘平原の戦いは、歴史書には記録がない創作の戦役です。戦国時代に秦と趙の間で局地戦があった可能性はありますが、具体的に「蛇甘平原」と呼ばれる戦いは確認されていません。
「キングダム」の作品内でのこの戦いは、信の成長を描き、王騎や飛信隊の存在感を際立たせるために設定された物語的な装置です。歴史の大枠につながる導入部分として重要な意味を持ちながらも、フィクションとして楽しむべき場面と言えます。
2-3. 六大将軍という称号は史実には存在しない
『キングダム』で繰り返し語られる「六大将軍」という称号は、史実の資料には登場しません。秦には白起や王齕など歴史に名を残す将軍が多く存在しましたが、制度的に「六大将軍」として任命された証拠はありません。
物語では、この称号が秦軍の強さの象徴として描かれ、若手将軍の競争や後継世代の活躍を盛り上げる要素となっています。つまり、六大将軍は史実に基づくものではなく、物語をドラマチックにするための創作だと受け止めましょう。
2-4. 王騎はほとんど活躍した記録が残っていない
作中で圧倒的な存在感を放つ王騎将軍ですが、史実にその活躍を裏付ける記録はほとんどありません。『史記』などにも王騎に対応する将軍の大きな戦歴は残っていないため、王齕や王翦といった複数の実在の将をもとに創作された人物と考えられます。
漫画では信の師として影響を与える重要人物に描かれていますが、これは史実に乏しい記録を逆手に取り、物語上のカリスマとして再構築されたものだと言えるでしょう。
2-5. 河了貂や漂は史実には存在しない
河了貂や漂は、史料には登場しない創作キャラクターです。李信の生い立ちは史実では詳しく残されていないため、物語上の必然から彼らが配置されたと考えられます。
漂は信の動機付けを担い、河了貂は軍師として飛信隊を支える役割を果たします。史実にいない人物であっても、物語に人間味やチームの結束をもたらし、読者が感情移入しやすくなるのが特徴です。
2-6. 羌瘣は史実では女性でない可能性が高い
羌瘣は作中で女性剣士として描かれますが、史実に同名の女性将軍は確認されていません。羌族出身の将軍が秦に仕えた可能性はあるものの、性別や活躍の詳細は不明です。
春秋戦国時代に女性が一軍を率いた記録は極めて少なく、羌瘣の人物像は創作の要素が大きいと考えられます。それでも彼女は物語に緊張感を与え、信との絆を描く重要キャラクターです。史実の空白を埋める創作によって、物語に深みが加わっています。
まとめ
『キングダム』は史実を土台にしながらも、大胆な脚色によって人物や戦いの描写を豊かにしています。嬴政の人物像、六大将軍の設定、蛇甘平原の戦いなどは物語上の再構成であり、史料に基づく史実とは大きく異なる部分です。一方で、秦がわずか10年余りで中華統一を成し遂げた事実や、各国が滅んでいく順番は史実に忠実に描かれています。
史実を踏まえて読むことで、創作部分との違いが明確になり、作品の持つドラマ性やテーマ性が一層際立ちます。史実との重なりを知ることで、歴史を学びながらエンターテインメントとしての物語を楽しめるでしょう。
※当記事は2025年9月時点の情報をもとに作成しています