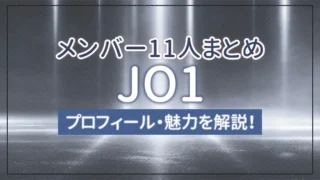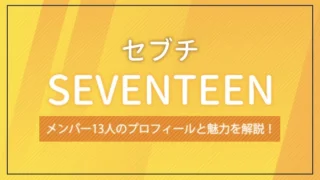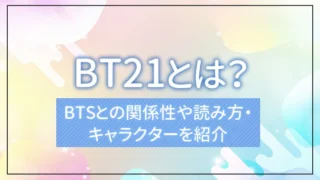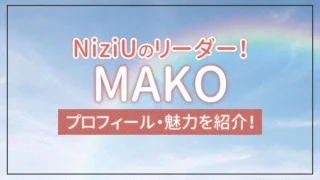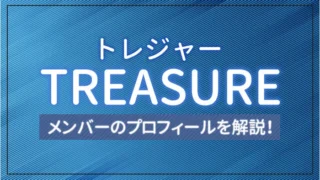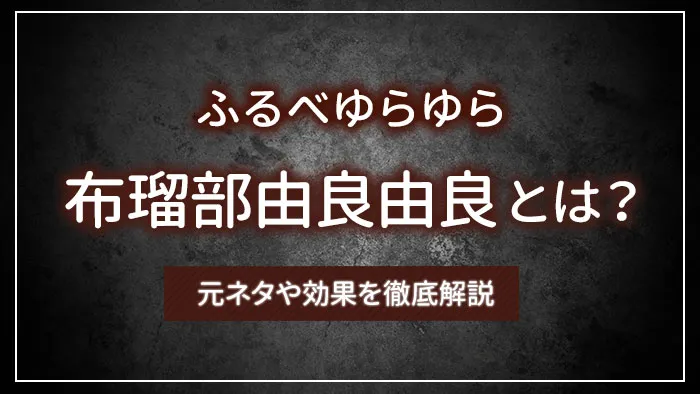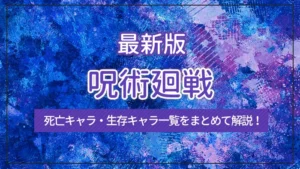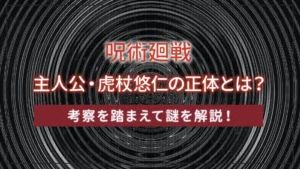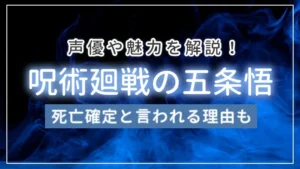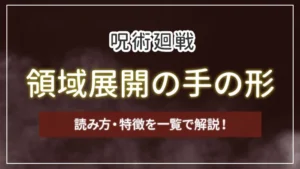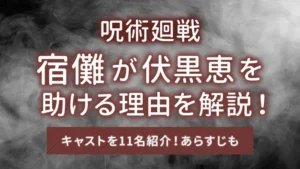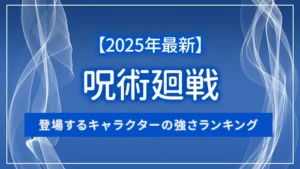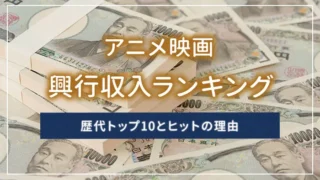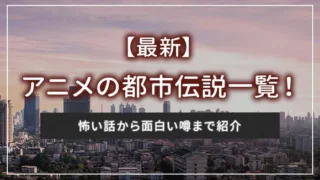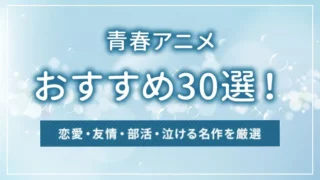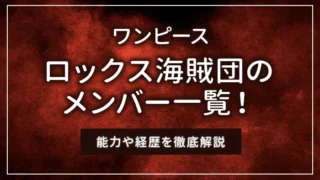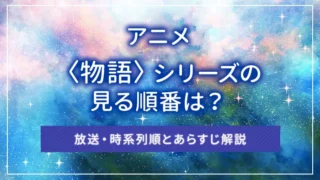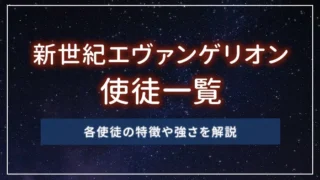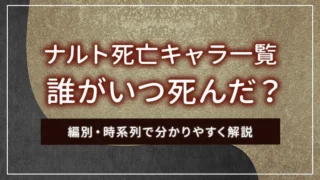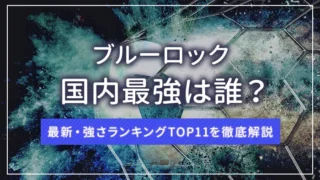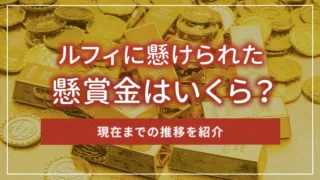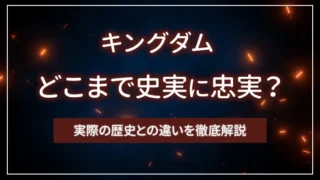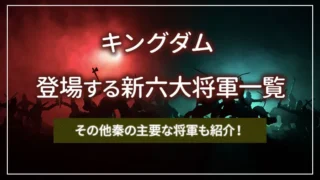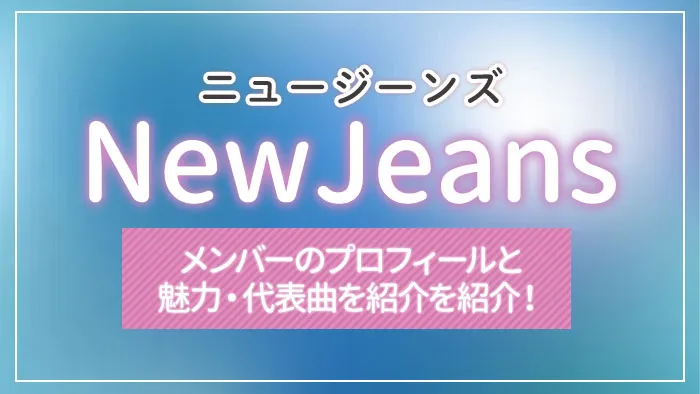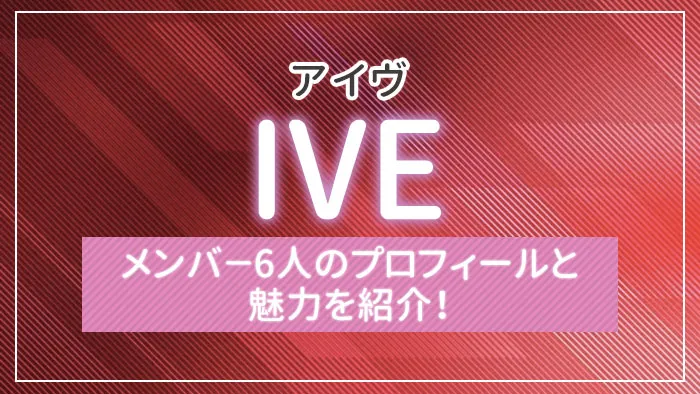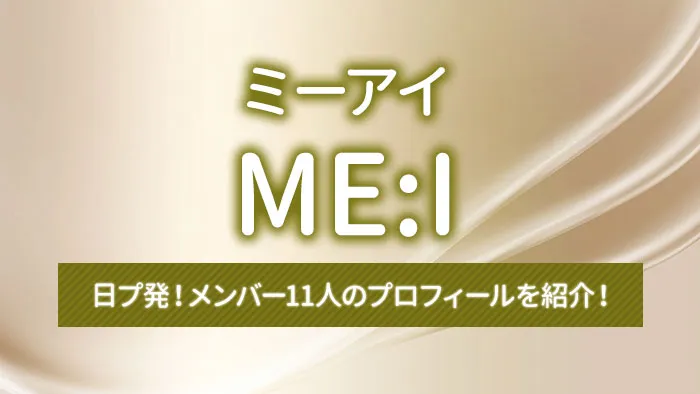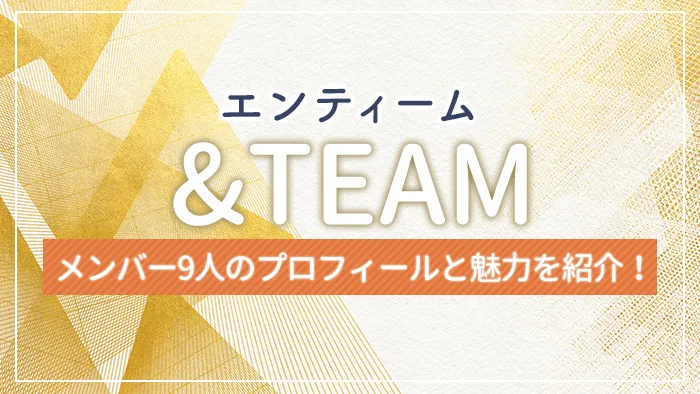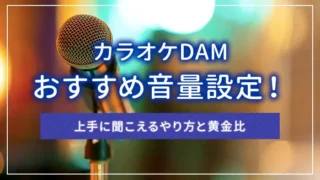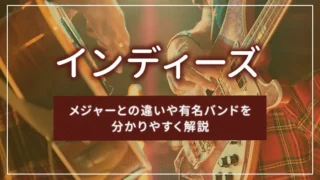アニメ・漫画「呪術廻戦」には、数多くの印象的な術式や技が登場します。その中でも特に注目を集めているのが、伏黒恵が使用する「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」です。この祓詞は、禪院家相伝の術式「十種影法術」における奥義であり、最強の式神・魔虚羅(まこら)を呼び出すために唱えられます。召喚者自身も攻撃対象になる危険な技で、事実上は自爆覚悟の切り札として描かれてきました。
当記事では、その登場シーンや魔虚羅の能力、召喚条件、神話的な背景について詳しく解説します。
1. 布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)とは
呪術廻戦は、人間の負の感情から生まれる「呪力」を扱う呪術師と、呪力から生まれた呪霊との戦いを描く人気作品です。主人公・虎杖悠二や呪術高専の仲間たちが壮絶な戦いに挑む姿が描かれています。
その中で、伏黒恵が使用する「十種影法術」は禪院家相伝の術式で、影を媒介に式神を召喚する技です。「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」は、その中でも最強とされる式神・魔虚羅(まこら)を呼び出すための祓詞。魔虚羅は歴代の使い手が誰も調伏できなかった存在で、召喚=自爆覚悟の切り札とされます。伏黒が命を懸けて使う奥義的存在として描かれています。
1-1. 布瑠部由良由良の登場シーン
「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」が初めて唱えられそうになったのは2巻9話、宿儺が虎杖の体を乗っ取った場面です。伏黒は格の違いを痛感しつつ奥の手を使おうとしますが、虎杖が正気を取り戻したことで中断しました。
次に唱えかけたのは7巻58話、八十八橋での特級呪霊戦。死を覚悟するも五条の言葉を思い出し、術を止めて領域展開を初披露します。
実際に完全発動したのが渋谷事変(14巻117話)です。重面春太との戦闘で絶体絶命に追い込まれた伏黒は「布瑠部由良由良 八握剣異戒神将 魔虚羅」と唱え、制御不能の最強式神を召喚しました。伏黒は仮死状態となりますが、その後宿儺が介入し、魔虚羅は討ち倒されます。
2. 布瑠部由良由良で呼び出される最強の式神・魔虚羅とは
#呪術廻戦 じゅじゅずかん
— 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) November 29, 2023
八握剣異戒神将魔虚羅(式神)
【歴代の十種影法術師全員が未調伏の式神】 pic.twitter.com/jTX1UNujX9
魔虚羅(まこら)は「十種影法術」で最強とされる式神で、歴代の術者も調伏できなかった存在です。圧倒的な力と適応能力を持ち、召喚には術者の命も危うくなる「布瑠部由良由良」の祓詞が必要です。ここからは、魔虚羅の能力や召喚条件、宿儺が倒せた理由、さらに他の式神について解説します。
2-1. 魔虚羅の能力
魔虚羅(まこら)は十種影法術で召喚される最強の式神で、歴代の術師が誰一人として調伏できなかった存在です。その根幹能力は「頭上の法陣を回転させることで、あらゆる事象に適応する」というもの。一度受けた攻撃は次から通用せず、性質の異なる現象にまで対応できるため、宿儺からは「最強の後出し虫拳」と評されました。
さらに右腕の退魔の剣は正のエネルギーを宿し、呪霊にとって致命的な武器となります。圧倒的な膂力とスピードを誇り、攻撃を受けても即座に適応してダメージを帳消しにするため、事実上「倒す手段が存在しない」と言えるチート級の式神です。
2-2. 魔虚羅を呼び出す条件
魔虚羅は、十種影法術の「調伏の儀式」を行うことで呼び出されます。召喚方法は他の式神と異なり、右腕に左拳を押し当て「布瑠部由良由良」と唱える特殊な手順が必要です。呼び出された瞬間に調伏の儀式が開始され、召喚者も敵も強制的に参加者となります。
魔虚羅を倒せば調伏できますが、歴代の術師で成功した者はおらず、召喚者自身も攻撃対象となるため極めて危険です。このため、魔虚羅は敵を道連れにする「自爆覚悟の奥の手」として描かれています。
2-3. 宿儺が魔虚羅を倒せた理由
魔虚羅は、頭上の法陣を回転させることで「あらゆる事象に適応する」最強の式神です。宿儺は戦闘中にこの能力を見抜き、初見の攻撃で適応が完了する前に叩き潰す戦法を立案しました。
まず領域展開「伏魔御厨子」による無数の斬撃で魔虚羅の再生と適応を上回り、次に炎の術式「開(フーガ)」を放ち、とどめを刺します。斬撃と炎という系統の異なる飽和攻撃を立て続けに浴びせたことで、歴代の術師が誰も倒せなかった魔虚羅を圧倒的な力で討ち破りました。
2-4. 十種影法術のその他の種類
伏黒恵が使う「十種影法術」は、その名の通り10種類の式神を操る術式です。式神を使うには「調伏」と呼ばれる儀式で勝利する必要があり、調伏に成功すれば召喚や合体、同時展開が可能となります。各式神は攻撃・防御・支援といった役割を担い、戦況に応じて使い分けることで戦闘を有利に進められます。以下に十種影法術の式神をまとめます。
| 式神名 | 特徴・能力 |
|---|---|
| 玉犬・白 | 探知能力に優れるが破壊され消滅。 |
| 玉犬・黒 | 戦闘と索敵に活躍。白と対になる存在。 |
| 玉犬・渾(こん) | 白の力を継いで誕生。高い攻撃力と俊敏性を持つ。 |
| 鵺(ぬえ) | 飛行能力を持つ怪鳥。電撃攻撃が可能。 |
| 大蛇(オロチ) | 巨大な蛇。宿儺に破壊され消滅。 |
| 蝦蟇(がま) | 巨大なカエル。仲間を匿い救出する能力を持つ。 |
| 不知井底(せいていしらず) | 鵺と蝦蟇を合体させた拡張術式。再召喚が可能。 |
| 満象(ばんしょう) | 巨大な象。踏み潰しや水流攻撃を行う。 |
| 脱兎(だっと) | 大量の兎を召喚し、撹乱や陽動に使用。 |
| 魔虚羅(まこら) | 最強の式神。歴代使い手も調伏不能。適応能力で無敵に近い。 |
十種影法術は、式神ごとの個性をどう組み合わせるかがポイントです。たとえば「脱兎」で敵を翻弄し、「満象」で一気に制圧するなど連携も可能です。最強の「魔虚羅」は特別であり、召喚は術者の命を危険にさらす「布瑠部由良由良」の祓詞が必要となります。伏黒の戦いは、この多彩な式神をどのように活用するかにかかっています。
3. 布瑠部由良由良・魔虚羅の元ネタ
布瑠部由良由良や魔虚羅には、日本神話や古代文献に由来する元ネタがあります。祓詞や神宝に関連づけられており、作中での神秘的な位置づけを深めています。以下でそれぞれのルーツを解説します。
3-1. 布瑠部由良由良の元ネタ
伏黒恵が唱える「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」は、日本神話に登場する「十種神宝(とくさのかんだから)」に由来すると考えられます。古代の祓詞「布瑠の言(ふるのこと)」では、死者を十種神宝の1つ「品々之比礼」に寝かせ、「布留部由良由良止 布留部」と唱えながら「死返玉」を振ることで蘇生させられると伝わっています。このことから“死者蘇生の言霊”とも呼ばれる言葉です。
「布瑠部」は宝を振る動作を、「由良由良」は玉が揺れて鳴る音を表すとされ、実際に玉犬の額には「道返玉」など十種神宝の玉の紋様が刻まれています。作中の祓詞も、この古代伝承をモチーフにしたものだと言えるでしょう。
3-2. 魔虚羅の元ネタ
伏黒恵の術式「十種影法術」は、日本の史書「先代旧事本紀」に記された「十種神宝(とくさのかんだから)」をモチーフにしています。十種神宝は鏡・剣・玉・比礼からなる霊力を宿す宝物で、式神の額に刻まれる紋様もこれに対応しています。魔虚羅はその中でも唯一の剣「八握剣(やつかのつるぎ)」にあたり、悪霊を祓う力を象徴します。実際に魔虚羅の武器も呪霊に致命傷を与える「退魔の剣」で、神話の設定とリンクしています。
さらに、仏教における十二神将の一柱「摩虎羅大将(まこらたいしょう)」も元ネタの1つとされます。摩虎羅は人の体に蛇の首を持つ姿で表され、作中の魔虚羅のデザインとも共通しています。こうした神話や仏教的要素が組み合わさることで、魔虚羅は“最強の式神”として描かれています。
まとめ
「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」は、伏黒恵が命を懸けて唱える祓詞で、十種影法術最強の式神・魔虚羅を呼び出す奥義です。
魔虚羅は「あらゆる事象に適応する」能力と正のエネルギーを宿した退魔の剣を持ち、歴代術師が誰も調伏できなかった存在。召喚は自爆覚悟の最終手段であり、作中でも渋谷事変で初めて完全発動しました。元ネタは日本神話の「十種神宝」や仏教の「摩虎羅大将」にあり、呪術廻戦の神秘性を深めています。
※当記事は2025年9月時点の情報をもとに作成しています